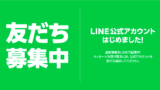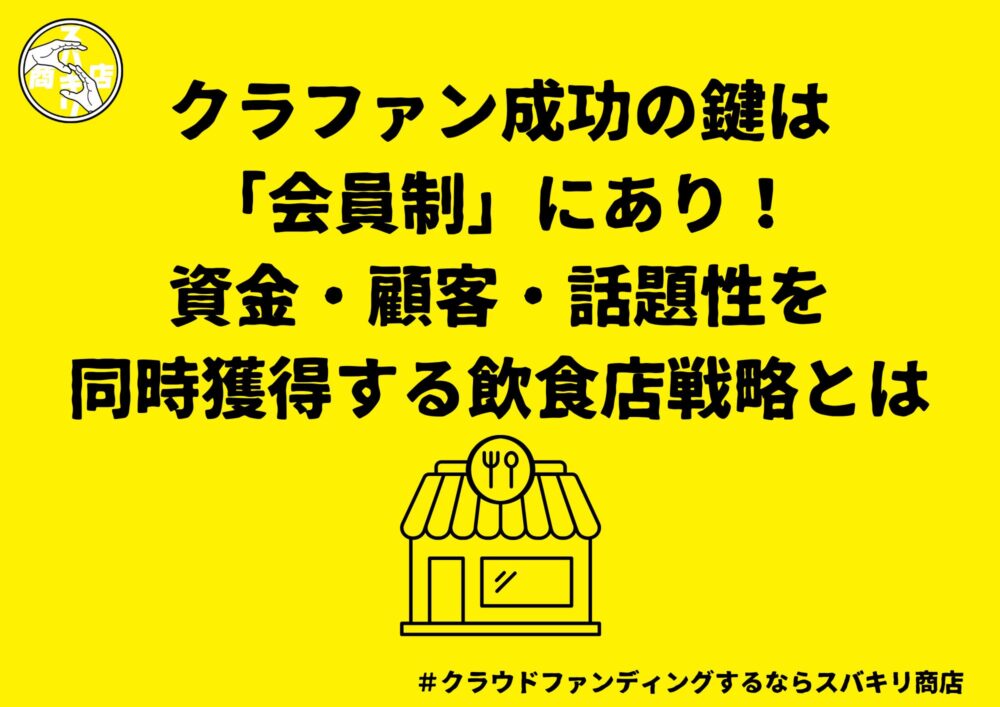飲食業=ハイリスクで儲からない
…本当にそうですか?
実は今、【会員制飲食店×クラウドファンディング】の組み合わせで、
“資金・顧客・話題性”の3つを同時に手に入れて、開業するケースが増えています。
会員制飲食店のクラウドファンディングで支援が集まる理由と成功事例を解説します。
なぜ今、会員制飲食店×クラウドファンディングなのか?
「飲食業は儲からない」——これは多くの経営者が抱く先入観です。実際、一般的な飲食店の廃業率は高く、人手不足や原材料高騰など、経営課題は山積みです。
しかし、ここ数年「会員制モデル」と「クラウドファンディング」を組み合わせることで、開業前から顧客と資金を確保し、リスクを最小限に抑えた飲食店経営が実現するケースが増加傾向にあります。
特に、他業種で経営経験を持つ方にとって、クラウドファンディングを活用した飲食店経営は、ブランディングや事業ポートフォリオ拡張の一環としても注目すべき戦略です。
会員制飲食店とは?通常の飲食店との違い
会員制飲食店は、「誰でも入れる飲食店」ではなく、「選ばれた人が定期的に通う空間」を提供するモデルです。
月額会費や事前購入型のチケット制などで売上の見通しが立てやすく、以下のような特徴があります。
- 安定した収益構造(予約・会費ベース)
- リピーター中心の運営(マーケティングコスト削減)
- 顧客との関係性が深い(コミュニティ形成)
また、予約制や事前決済制を徹底することで、会員数や提供内容を管理しやすく、食材ロスや人件費の最適化も行えるため、スモールスタートに適しています。
なぜ会員制飲食店とクラウドファンディングが相性抜群なのか?
会員制飲食店の立ち上げは、その飲食店が提供したい「共感」や「限定性」といった感情的価値と密接に関係しています。これはまさに、クラウドファンディングが得意とする領域です。
クラウドファンディングは、共感をベースとした資金調達手段です。会員制という限定性を支援の見返りで提供することで、支援者に精神的な満足感や特別感を与えることが出来ます。
その他にも以下の3つのメリットがあります。
- 顧客=支援者=ファンという関係を開業前から築ける
- コンセプト・ビジョンに共感した人が支援・予約してくれる
- 資金調達だけでなく、認知拡大・初期顧客の確保・市場テストのマーケティングを同時に実現
融資とは違い、返済義務がないのも大きなメリットです。
「こんな店があったら通いたい」という声を具体的に集められ、フィードバックしたデータを経営課題として活用できます。
支援を集めるために重要な2つの設計を工夫する
クラウドファンディングを成功させるには、1人でも多くの支援を集める必要があります。そのためには、共感を生むストーリー設計と、支援する動機付けとなるリターン設計の2つを工夫することが肝心です。
工夫その① 独自性のあるストーリー設計で共感を集める
クラウドファンディングを成功させるには、独自性のあるストーリーを設計し、共感を集めることが欠かせません。なぜ敢えて、会員制飲食店に挑戦するのか。その理由や想いを丁寧に伝えることが必要です。
例えば、このようなストーリーを提示できるでしょう。
- 「地域の生産者とのコラボがしたい」
- 「会員制で“つながり”の場を提供したい」
- 「飲食を通じて新しい価値創造をしたい」
ここ数年、健康や環境配慮、地域課題といった社会問題的な部分から、食に対する意識や興味関心がますます多様化しています。
食には、たくさんのストーリー性が秘められています。食材だけでなく、複数の要素を組み合わせることで、独自性のあるストーリー設計をすることが、クラウドファンディングを成功させるカギになります。
ストーリー設計に必要な2つのことについて、以下の記事で詳しく解説していますので、独自性のあるストーリー設計を知りたい人は是非お読みください。

工夫その② 支援意欲を高める魅力的なリターン設計
クラウドファンディングでは、支援することで得られるリターンの魅力や価値が重要です。特に、飲食店の場合、食べることは毎日の生活に欠かせない活動と言えます。高級食材や食品関連のリターンは魅力を感じやすく、比較的支援されやすい傾向がありますが、原価が発生するため粗利計算を徹底しましょう。
会員制飲食店では、「特別感」を強調したリターン設計が必要になります。今すぐは会員にならなくても、どんなお店なのがを知ったうえで、入会できる導線にもなる体験リターンなども用意しておくことも重要です。
- 限定会員権(年会費制)
- 初回予約優先権
- 試食会・レセプション参加
- 名前入りメニューやネーミング権
思わず支援したくなるリターン設計には、「体験」や「限定」を重視した設計がされています。特に、最近では物品よりも、体験型リターンへの需要が伸びている傾向があるので、支援状況を分析し途中で追加できるリターンも用意しておくことをお勧めします。
リターン設計については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

実際の成功事例から学ぶ
スバキリ商店でプロデュースした会員制飲食店のクラウドファンディング成功事例から、支援が集まった理由を解説します。
事例1:沖縄の歴史と文化を体験できる会員制レストランバープロジェクト
初日になんと200万円の支援が集まった、沖縄料理の会員制レストランバーのクラウドファンディングです。

このプロジェクトは、沖縄県で生まれ育った 比嘉康二 さんが実行しています。
泡盛と琉球料理と歴史を楽しむ飲食店ですが、食べる、飲む行為の価値や、理論的なペアリング、何よりこの土地の人たちが積み重ねてきた飲食の価値を丁寧に伝え届けることを表現するレストランバーです。
実行者の SNS 投稿から、抜粋して掲載
長年、沖縄の泡盛専門店で働き、泡盛の魅力を国内海外へ伝え続けてきた比嘉さんが、泡盛をただ味わうだけでなく、その背景にある歴史や文化、琉球~沖縄の土地で受け継いできた伝統を理解することを提供する自分の店を持ちたいとクラウドファンディングに挑戦。
リターンは、5年会員権、10年会員権、永久会員権と、会員制飲食店らしい設計ながらも、どれも二桁超えの支援状況です。通常、飲食店でのクラウドファンディング平均支援額は、1万円前後ですが、このプロジェクトは一番人気のリターンが10年会員権の22,000円。このリターンだけで150万円以上の支援が集まっています。
このプロジェクトが多くの支援を集め続けているのは、これまで実行者が泡盛を通じて多くの人と交流し、沖縄の文化を愛している姿勢を見せてきたことにつきます。
また、琉球王朝の宮廷料理や伝統の強い共感をもち、実行者を応援したいという沖縄好きや泡盛ファンがたくさんいるという証拠です。
「クラウドファンディングは実行者の信用を換金する装置」という表現がありますが、まさにその見本といえる事例です。
初日200万、ネクストゴール300万達成、次は500万と、どこまで支援が伸びるのか注目のプロジェクトです。
事例2:バーテンは僧侶!還暦記念会員制×紹介制バー開店プロジェクト
こちらは、経営者であり僧侶である男性が挑戦した、還暦記念の会員制かつ紹介制のバー開店プロジェクトです。

実行者は、福岡県北九州市で飲食店を経営する 進龍圓 さん。「自分の人生には、なにもない」という欠落感から50代で修験道の道に入り、得度。
僧侶とバーテンダーは役割が一緒だという視点から、駆け込み寺としてのバーを還暦から始めたいとクラウドファンディングに挑戦することを決意。
煩悩の数とされる108人限定の会員制ということで、リターンも会員権2種類を108人分用意。T シャツや実行者の半生を振り返る手記など、遠方からの支援にも対応した設計もされています。
目標額は30万円でしたが、実行者の人生の集大成という意気込みと還暦を祝いたいという関係者からの支援が集まり、目標額の4倍に近い約115万円の支援が集まりました。
こちらも一番人気のリターンは15,000円の会員権でしたが、12名限定の VIP 会員権50,000円が8名から支援されているため、支援総額を押し上げる要因となっています。
飲食店=ハイリスク&ローリターンではなく「資産化できる事業」
これまでの常識は、飲食店 = ハイリスク&ローリターン とされてきました。
確かに、一般的な飲食店は利益率が低く、過酷な労働環境とされがちです。天候や景気など環境要因にも大きく影響を受けますし、物件費や人件費など固定費の占める割合が大きいというデメリットもあります。
しかし、以下の条件を満たすと、飲食店は「資産化できる事業」になります。
- 固定ファンを持つ小規模運営
- 副業や他事業と連携したシェア運用
- 「わざわざ体験したい」と思わせる独自のブランドストーリーがある
本業で培ったブランド力や顧客ネットワークを活かせば、事業コストを抑えた上で高付加価値を提供できます。
その仕組みを作るうえで、クラウドファンディングは活用できるのです。
会員制飲食店に関するよくある質問(Q&A形式)
会員制飲食店に関する2つの質問を取り上げます。
クラウドファンディングに関するよくある質問は、以下の記事にまとめていますので、そちらをご確認ください。
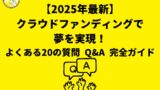
Q1. 会員制って法律的に問題ない?
会員制飲食店は特別な体験を提供する魅力的なビジネスモデルですが、一般の飲食店とは異なる法律上の注意点があります。
会員制飲食店を運営する上で、一般の飲食店と同様の法的手続きに加え、会員制という形態ならではの法律上の注意点があります。
飲食店営業許可やアルコール提供の許可取得は基本です。
特に接待を伴う場合は風営法の対象となり、営業時間の制限や許可証の掲示義務などが発生します。
また、会員規約の設計においては、法的拘束力の限界があることを理解し、公序良俗に反しない内容とすることが重要です。会員情報など個人情報保護への配慮も忘れてはなりません。
これらの法的要件を遵守しながら、他店と差別化されたその店だけのサービスを提供することが、会員制飲食店の運営で重要な鍵となります。
法令遵守は単なる義務ではなく、長期的な経営の安定と信頼構築のための基盤です。定期的に関連法規の変更を確認し、必要に応じて運営方法を見直すことが大切と言えます。
Q2. 本業がある中で別事業として運営するのは無理では?
本業の傍らで飲食店を運営しているケースはよくあるケースです。
会員制飲食店であれば、営業日・会員数を制限することで兼業も可能です。実際に、月4回営業や短時間営業などの運営スタイルで成功している事例もあります。
例えば、メインとなる事業で活用できる要素がある、社内の福利厚生になるなどのメリットがあるが、財務上リスクが高いと判断すれば、クラウドファンディングを活用してテスト運営できるかを判断するという選択肢もあります。
クラウドファンディング活用で資金と顧客と話題性を手に入れる
クラウドファンディングを活用することで、資金と顧客と話題性を一度に手に入れれば、事業の幅を白げることが出来ます。
「飲食業はリスクが高い」という考えは、従来型のビジネスモデルに基づくものです。
しかし、会員制×クラウドファンディングという新しい手法を使えば、
- 資金リスクの低減
- 顧客の先行確保
- 話題性の創出
という3つの武器を手に入れることができます。
その第一歩は、「応援される理由」を明確にすることから始まります。
もし、既存事業に関連でき、従業員の福利厚生や地域貢献につながる飲食店経営を検討しているなら、クラウドファンディングを活用することで事業化することが出来るかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会員制飲食店のクラウドファンディングプロデュースなら、スバキリ商店へ
クラウドファンディングは飲食店の開店や改装、移転などの資金調達に最適な仕組みです。
スバキリ商店では、会員制飲食店のプロジェクトや、店舗改装のプロジェクトのプロデュースを行っています。Instagram で、累計1400件以上に及ぶ様々なジャンルの過去プロジェクトを随時紹介中です。

忙しくても、大丈夫!ゼロから丸投げでクラウドファンディングに挑戦できるよう、経験豊富なスタッフがあなたの事業や活動を元に、プロジェクトページの作成から告知のサポートまでお手伝いします。
kindle でクラウドファンディングの電子書籍も出版しました。
詳しいご相談は、公式 LINE からお気軽にどうぞ。